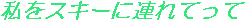
|
人の多い白銀のゲレンデを、聞仲は温かい紅茶を飲みながら眺めていた。 目線の先にあるのは巨大な人の姿。 それは濃紺の真新しいスキーウェアを着た飛虎だった。 彼は冬の日差しを浴びながら器用に人の間をすり抜けて滑っていく。 果たしてあれが初心者の滑りだろうか・・・。 心の中で呟いた言葉を溜息とともに吐き出した聞仲は、このスキー旅行のきっかけとなった一ヶ月前のことを思い出していた。 「え・・・スキー?」 大きなエビフライに噛み付きながら飛虎は驚きの混じった声で聞仲の言葉を繰り返した。 週末になると交互にお互いの家に泊まりに行くことにしている二人。 この日は飛虎が聞仲の家に泊まりに来ていたのだった。 そして夕飯の最中にそれは起こった。 もごもごと口を動かしながら尋ねた飛虎の言葉にゆっくりとうなずく聞仲。 「実は、葉書が来たんだ」 そう言って料理の並ぶテーブルの隅の方に聞仲が差し出した一枚の葉書。 飛虎は箸を止めてそれを手にとる。 葉書は絵葉書で、裏には真っ白に雪化粧された山の姿とその麓に佇むロッジが映った写真が載っていた。 裏返して表を見ると、下半分に聞仲宛てたスキーへの招待の文面。 飛虎が誰なんだと尋ねるのを見透かしていたように聞仲が先に口を開く。 「その差出人は私が学生時代から世話になっているスキーのペンションのオーナーなんだ」 「ふーん、そうなんだ」 「そういえば、最近スキーなんて行ってなかったな」 小さく呟く聞仲の声を耳ざとく飛虎は聞いていた。 「・・・よっしゃ」 唐突に叫ぶ飛虎。 「な、なんなんだ一体」 「行こうぜ、スキー」 「・・・は?」 飛虎の言った言葉が理解できず、聞仲の動きが止まる。 「そうだな・・・今月はさすがに無理だから・・・来月だな」 飛虎はリビングの壁にかかっているカレンダーに目をやって日にちを確認する。 「ちょっ・・・ちょっと待て飛虎」 その時になってようやく頭の中で理解した聞仲が一人で計画を立てだした飛虎に口を挟む。 「急にスキーだなんて無理に決まっているだろう」 「いいじゃねえか、ちょうど来月あたり遠出しようって言ってたし」 「ペンションだって空いてないかもしれないし」 「それなら・・・」 そう言って突然席をたつ飛虎。どこに行くのだろうと視線で追いかける聞仲。 「ほらよ、電話すればいいじゃねえか」 飛虎は子機を持って再び聞仲の向かいに座る。 「・・・」 そして聞仲は葉書を見ながら電話を掛けたのだった。 「どうだった?」 電話が終わり、飛虎が聞仲に嬉しそうに尋ねる。 「・・・私の電話のやり取りを聞いてわかっただろう」 「だから、どうだったって聞いてんだよ」 私の口から聞きたい・・・そんなところか。 そう敏感に感じ取った聞仲は小さく溜息をついて答える。 「・・・今月はもう予約でいっぱいらしいが、来月ならまだ空きがあるそうだ」 「よっしゃ、決まりだな」 飛虎がぱちんと指を鳴らす。 その後聞仲はもう一度電話をする羽目になったのだった。 それから夕飯をすませリビングに移動した二人。 そこで聞仲はふとした疑問を飛虎に投げかけた。 「飛虎、板は先に送るか?」 「板?俺そんなもん持ってねーぞ」 「・・・ウェアは?」 その問いにも首を振る飛虎。 「もしかしたら・・・お前・・・スキー・・・」 「おうっ、初めてだ」 そう言って大声で笑う飛虎。傍にはうなだれる聞仲。 「なんだよ、そのシケた面はよ」 だらりと下がっていた聞仲の腕を飛虎が思い切り自分の方へと引っ張った。途端にバランスを崩した聞仲は易々と飛虎の腕の中に掴まってしまった。 「なんなんだ、お前はっ。離せっ」 飛虎の腕から逃れようともがく聞仲を更に抱き締める飛虎。 「お前が・・・教えてくれるんだろう」 不意に耳元で囁かれた言葉に聞仲の動きが止まる。 「な?」 無言の聞仲にたたみかけるようにもう一度聞く飛虎。 「・・・私の指導は厳しいからなっ」 そう言って抵抗することを止める聞仲。 「お手柔らかに頼むぜ、聞仲コーチ」 そう言って飛虎は僅かに朱くなっている恋人の頬に唇を寄せたのだった。 それからの週末はスキー旅行への準備で殆ど時間を費やした。 飛虎はまた行くだろうと言ってスキー板まで買ってしまった。 ウェアは聞仲も新調し、同じ形の色違いで飛虎は紺、聞仲は水色を買ったのだった。 顔を合わせるといつもスキーの話ばかりをして、買ってきたスキー雑誌を二人で見ることもあった。 そしてそんな事をしている内に、当日がやってきたのだった。 思えば・・・早かったな。 そう締めくくり、聞仲は回想を止めて窓の外を見る。 しかし探し出そうとしている紺色のウェアは何処にも見当たらなかった。 どこに言ったんだ? と、そのとき誰かが肩を叩いた。 振り向くとそこにいたのは探していた張本人。 「よっ」 飛虎は持っていたトレイを聞仲の目の前のテーブルの上に置いた。 「それにしても・・・凄い量だな」 聞仲は空になったカップを端に寄せて飛虎の置いたトレイの上に乗った料理を見回した。 そこにはゲレンデのレストランには定番のカレーライスやうどん、ポテトにホットドックが並んでいる。端に目をやるとなんとアイスクリームまであったのだ。 「アイスクリームなど食後に買えばよかったじゃないか、融けてしまうぞ」 聞仲の言葉に飛虎がその存在を思い出す。 「それは俺が食べるんじゃなくて、ほらよ」 そう言って飛虎は聞仲にアイスクリームを手渡した。 「これ好きだろう?」 手渡されたアイスクリームを良く見ると確かに聞仲が好んで食べる銘柄のそして味のアイスクリームだった。 「この中結構あったかいし、丁度いいだろう?」 そして透明のスプーンを差し出す。 「俺が食べ終わるまでそれ食べて待っててくれよな」 にやりと笑う飛虎を見て、聞仲はその時自分がどんなに嬉しそうな顔をしてアイスクリームを見ていたかに気がついた。 「こっ・・・子ども扱いするな!大体こんなに食べるってことは、スキーに飽きたということか?」 聞仲は恥ずかしさのあまり何の罪もないアイスクリームにグサリとスプーンを刺し、口へと運んだ。 口の中に広がる甘さと冷たさ。 「んなわけねーだろ。これは午後からの栄養補給」 言いながらスプーンでカレーを次々とすくっては食べていく飛虎。 「だって俺、午前中はずっと聞仲に教えてもらってたからな」 「ああ・・・教え甲斐のない生徒だったよ、お前は」 飛虎の何気ない一言に聞仲は少し拗ねた声で呟いた。 やべ・・・聞仲のやつ、拗ね始めやがった。 聞仲が拗ね始めた原因・・・それは飛虎の人間離れした運動神経にあった。 聞仲が飛虎にスキーの滑り方を教えて数時間。こける回数と聞仲にちょっかいを出して殴られる回数が二桁に届く頃には飛虎はスキーを殆どマスターしていたのだ。 「それはお前の教え方が良かったからだよ、他の奴に教えてもらってたらまだボーゲンくらいしか滑れなかったって」 「そうか?」 「そうだよ」 「・・・そうか」 真顔で言う飛虎の言葉にどうやら少しは機嫌が直ったのか、聞仲は再び手にしたアイスを一口すくった。 「だからさ、午後からまた滑ろうぜ。今度はリフトに乗ってさ」 「ああ、そうだな」 自分の言葉をいともあっさりと承諾する聞仲に心の中でほっと安堵の溜息をついた飛虎。 しかしその安心は次の瞬間いとも簡単に崩れるのだった。 「乗るリフトは勿論あれだろう?」 そう言って聞仲が指を刺したのは、彼の背後にあった上級者用のリフト。 「・・・マジ?」 「私が冗談を言うとでも?」 にこりと笑う聞仲だったが、目は笑っていなかった。 「飛虎も滑れるようになったし、問題ないんだろう?」 その言葉が決定打となり、飛虎は白旗を振る以外に道は残っていなかったのだった。 「・・・こ、怖え・・・」 一時間後、二人がいたのは言葉どおりの上級者用ゲレンデ。 初級者用のなだらかで障害物のまったくないゲレンデとは違い、急斜面でしかも所々に小さな丘のようなものがあるこの上級者用のゲレンデに飛虎は内心焦っていた。 俺・・・生きて降りることできるのか・・・。 そんな飛虎を聞仲が見上げる。 「どうした飛虎、顔色が悪いぞ。もしかして・・・怖いのか?」 挑戦的な視線に飛虎が虚勢を張る。 「んなことあるわけねーだろうが。こんな斜面すぐに降りてやらあ」 「それはそれは勇ましいものだな。では先に行くぞ」 そう言うと聞仲はゴーグルをはめて斜面を滑り始める。 さすがに慣れているだけあって聞仲は障害物をうまく避けてどんどんと降っていく。 「さすがだな・・・って俺もこんなことしてる場合じゃねえんだよな」 聞仲の滑りに見とれていた飛虎はすでに彼が三分の一ほど下っていることに気がつく。 「ま、なんとかなるだろう」 そう呟いて飛虎はゴーグルをはめてストックに力を入れたのだった。 「だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ」 が、斜面は思った以上の急勾配で、身を躍らせた瞬間から重力に従いどんどんとスピードがつきはじめる。 結果制御不能となった体は無様にも雪の斜面へダイビングしてしまうのだった。 「なんのっ、これしきっ」 すぐに起き上がると飛虎はまた滑り始める。しかしすぐに同じ様に斜面に体をぶつけることになる。 その姿は『滑る』というよりも『転げ落ちる』といった方がいいのではないかというほどであった。 「・・・やはり、まだ早かったか」 ゲレンデを半分ほど降りてしまった聞仲はそんな飛虎の姿を見ながら呟いた。 少々度が過ぎてしまったかな・・・。 そんなことを心で呟いて聞仲は苦笑する。 先ほどこのゲレンデを選んだのは少し天狗になっている飛虎を懲らしめてやろうと思ったいたずら心と、もしかしたら飛虎なら滑れるのではないかという期待からであった。 しかしよくよく考えると飛虎はまだ半日もスキーを滑っていないのだ。 聞仲は少しだけ自分の行いを反省する。 下まで降りたら先程曲げた機嫌を直してやろう。 そんな事を考えながら聞仲は再び麓まで降り始める。 右へ左へと小さなこぶを避けて滑っていく聞仲。そのとき何度目かの飛虎の絶叫が耳に入った。 どうやらかなり苦戦しているようだな。 聞仲は滑りながらちらりと後ろを振り返り小さく笑う。 しかしその油断が聞仲の足元をおぼつかなくさせたのだった。 気がつかなかった小さな雪の丘が、視線を戻した聞仲の目の前に立ちはだかっていた。 「しまっ・・・」 思ったときには既に時遅く、聞仲はその丘を避けきれず、中途半端なジャンプをしてしまう。 次の瞬間聞仲が感じたのは身体への強い衝撃。 そしてそのまま聞仲の目の前は真っ白になったのだった。 「・・・っててて」 頭をさすりながら起き上がって眼下を見下ろしたとき、聞仲の空色のウェアが変な方向に移動するのを飛虎は確認した。 何だかんだ言ってあいつだってこけるんじゃねーか。 「おーい、大丈夫か?」 からかい気味に叫んでみる飛虎だったが、聞仲は答えない。それどころか水色のウェアは動こうともしない。 「聞仲?」 その様子にようやく不信感を抱いた飛虎は急いで体を起こす。 あいつ・・・もしかして。 そう思った瞬間、飛虎は勢いをつけながら斜面を降り始める。 聞仲! 何度か転びながらも今までとは比べ物にならない時間で飛虎が聞仲の元まで降りていく。 「聞仲!」 彼の空色のウェアが段々とはっきり見えると、飛虎は聞仲の名前を大声で叫んだ。 その声に今まで動かなかった体がゆっくりと動き出す。 「飛虎」 そして上半身を起こした聞仲が飛虎の姿を確認する。 「おい、大丈夫なのか?」 心配そうに聞仲の傍に立つ飛虎。 「私としたことが・・・別に大した事はない。少し意識が飛んだだけのようだ」 照れ笑いを浮かべながら聞仲が立ち上がろうとする。 「しかしお前もすごいもんだな。私が意識を失っていたのはほんの僅かな・・・っ」 立ち上がりかけたその時、聞仲が再びその場に崩れ落ちる。 「聞仲っ!」 その彼の腕を掴み飛虎が支える。 「すまない」 「お前どっか怪我したんじゃねーのか」 飛虎が足元を見下ろすと、聞仲は右足をかばうように立っていた。 「もしかして・・・」 「足首を捻ってしまったようだ。折れてないはずだから大丈夫だ」 「何言ってんだよ!」 そう言うのが早いか、飛虎は自分と聞仲の履いていた板を取り外した。 「飛虎!」 それから飛虎は木の傍にストックと板を突き刺すと、聞仲に背を向けた。 「そんなことしなくても大丈夫だ。滑って下まで降りる!」 「馬鹿野郎!そんなことして捻挫が悪化したらどうするんだ」 怒鳴りつけられ聞仲は反論できない。 「早く俺の背中に乗れ。拗ねるんなら後で拗ねろ。今はそんな事言ってられねえんだ」 飛虎の真剣な声に聞仲はゆっくりと飛虎の背中に負ぶさる。 そして飛虎はゆっくりと麓へと降りていく。 雪を踏みしめる音が聞仲の耳へ届いてくる。 「・・・重くないか?」 「重くなんてねえよ。それよりさっきは言い過ぎた、すまねえ」 「別に・・・怒っていない」 言葉を交わしながらも飛虎の歩調はまったく変わらない。 「痛くねえか?」 「少しだけ、ズキズキするが大丈夫だ」 言いながら聞仲は右足首に意識を向ける。足首は熱を持ちながら痛みを訴えていた。 そして再び静寂。 「ありがとう・・・」 小さく呟いた聞仲の言葉は飛虎に届いたのか届かなかったのか、飛虎は何も言わず歩き続けたのだった。 真っ黒な鏡のような窓を聞仲はひとりぼんやりと眺めていた。 窓の外では日が暮れた頃から降り始めた雪が舞を舞っているように降り続いている。 「あー、いい湯だったぜ」 部屋のバスルームのドアが開いて飛虎が出てきた。 「まだ雪降ってんのか?」 座っている聞仲の上からひょいと窓の外を見る飛虎。 「降ってるなー」 そして笑って聞仲を見下ろした。 しかし聞仲の表情は曇ったままだ。 「なーにしけた顔してんだよ」 「すまない・・・こんなことになるなんて」 聞仲は自分の右足に視線を向ける。 巻かれた白い包帯が更に痛々しく感じさせている。 数時間前、聞仲を負ぶって麓まで降た飛虎はすぐにペンションまで戻りオーナーへ聞仲の怪我を見せた。 医学の心得があるらしいオーナーは聞仲の足首を見て捻挫だと判断すると、湿布と包帯で今の状態にしたのだった。 聞仲の治療の間飛虎はもう一度ゲレンデに戻り二人分のスキー板とストックを持ち帰った。 そして今に至るのだった。 「すまない・・・」 もう一度聞仲が呟いた。 「だから、謝んなって」 飛虎がくしゃりと聞仲の髪をかき乱した。 「私がこんな怪我をしなければ飛虎はもっとスキーを楽しめただろうし。それに露天風呂だって入れたのに・・・」 このペンションには実は露天風呂があり、雪をすぐ傍にしながら湯につかることができるのだが、飛虎はそこに一人で入るのを拒んだのだった。 「別に一人で滑っても面白くねーよ。それに風呂だってどんなに景色が良くても、同じ気持を分かち合えなきゃ意味がねえし」 その言葉に膝の上に置かれた聞仲の両手が堅く握られる。 「それにな、聞仲」 優しい声に聞仲が顔を見上げる。 「ここは逃げねーんだからよ、また来りゃいいじゃねーか?」 「でもっ」 眉根を寄せて反論しようとした瞬間、聞仲の顔に飛虎の顔が降りてくる。 「もう、言うな・・・」 「んっ・・・」 そして塞がれる唇。 「聞仲・・・」 耳元で囁かれる飛虎の声に聞仲は首を竦める。 飛虎の唇が首筋を滑っていく。 「飛虎・・・っつ」 突然聞仲の顔が苦痛に歪む。驚いた飛虎が顔を上げる。 「・・・すまねえ」 「違っ・・・どうやら無意識のうちに右足を動かしたようで・・・」 二人の視線が聞仲の右足に集中する。 「・・・そりゃしゃーねーよな、よく考えたらお前怪我人だし。そうだっ、じゃあその代わりと言っちゃなんだけどよ」 それから首を傾げる聞仲の耳元で何かを呟いた。 「・・・!」 「駄目・・・か?」 聞仲はしばらく考えるように首を捻っていたが、どうやら決心がついたらしく顔を上げる。 「ちゃんと・・・連れて行けよ」 顔を真っ赤にしながら聞仲は飛虎に向かって両腕を広げた。 「了解」 飛虎はゆっくり笑うと聞仲の足に負担がかからないようにそっと彼を抱え上げた。 次の朝、聞仲は奇妙な感覚に目を覚ました。 何かが自分の体の、胸の辺りをさわる感覚。 「ん・・・」 何だ?一体・・・。 まだ眠たい目をこすりながら聞仲が掛け布団を捲る。 そこにあったのは浴衣の合わせ目から自分の胸の上を這っている腕。 「・・・!」 ギョッとして左を見ると飛虎の寝顔。 そういえば・・・昨日一緒に眠ったんだったな。 飛虎からの要求・・・一緒に眠ろう。 聞仲がそれを承諾したのは飛虎への詫びと感謝からだった。 「んー、聞仲ぅー」 はっと我に返る聞仲。飛虎は眠っているにもかかわらず聞仲の肌の感触が心地良いのか手をどけようとはしない。それどころか本当に眠っているのだろうかというほど手はあちこちを触っていく。 「・・・っこのっ」 私が馬鹿だった・・・私が・・・。 心の中でそう呟いて聞仲は左手に力を込めて拳を作る。 「馬鹿飛虎ー!」 そして次の瞬間聞仲は怒号と共に自分の健康な左足で飛虎をベッドから突き落としたのだった。 ◇◇終◇◇ ◇東儀より一言◇ 2002年冬のインテックスにて、さくらんうさぎ様のスペースで、くじ引き企画をやってらしたのですが、その時見事に1/30の確率で引き当てた「白さまへのリクエスト権」で、書いていただいた逸品です☆ 南国の方に雪国リゾートをリクエストする極悪非道にもかかわらず、本当に素晴らしい作品をいただいてしまいましたvv。 調子に乗る初心者飛虎に、拗ねてつい意地悪をしてしまう聞仲様がとても愛おしいです(^^) とってもらぶらぶなヒコブンをありがとうございました(^0^) |



